Catch-up 脱炭素化から経済成長
建設業に関わるトピックスを分かりやすく解説するコラム『Catch-up』最新号を掲載します。
バックナンバーはこちらよりご覧ください。
脱炭素化と経済成長を両立 「1.5度の約束」守れるか 2025/2/6
EUの気候情報機関は1月10日、2024年の世界平均気温が産業革命前と比べて1・5度上昇したと発表した。22年に宣言された「1・5度の約束」が守られるのか―。見通しは極めて厳しい。この危機に各国が対応する中、日本では「エネルギー基本計画」「地球温暖化対策計画」「GX2040ビジョン」が改定され、経済成長にもつながる脱炭素化が進められようとしている。
三つの計画は、脱炭素化に向けた計画として密接に関連しており、いずれも年度内に閣議決定される。エネルギー基本計画ではエネルギー政策の方向性、地球温暖化対策計画では国・地域・事業者などが温暖化を防止するために講じるべき取り組みなどを定める。二つの計画をまとめ、経済成長も同時に実現させようとする国家戦略がGX2040ビジョンだ。
計画に盛り込まれる施策を見ると、40年には、電源構成のうち4~5割を再生可能エネルギーとする目標を定めている。特に期待されているのは太陽光発電設備で、再エネ全体の22~29%程度を太陽光発電設備に頼る方針だ。
次世代再エネ技術の普及が重要とし、薄くて建築物の壁にも取り付けられるペロブスカイト太陽電池は40年までに約20ギガ㍗導入する。浮体式を含む洋上風力発電は、40年までに30~45ギガ㍗の事業を実施する。
道路やダム、上下水道などのインフラを活用した再エネの導入も取り組む。
住宅・建築物の分野では、「ストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能を確保する」という50年の目標を見据え、省エネ基準の段階的な水準引き上げ、新築建築物のZEH原則化、ZEHの定義見直しに取り組む。
建築物の建築から解体までのライフサイクルカーボンの算定に関する新制度や、取り組みの進め方も検討する。
GX2040ビジョンでは、大企業だけでなく中堅・中小企業が脱炭素に取り組むための支援策にも触れている。新たなビジネス創出だけでなく、経営資源が限られる中小企業や早期の脱炭素化が難しい産業などを取り残さず、GX産業構造へと公正に移行させることも重要な課題だ。
体育館の空調設置進める 能登半島地震を教訓に 2025/1/8
能登半島地震の被災地では4万人以上が避難所に身を寄せた。空調設備がない避難所や停電で暖房器具が使用できなかった避難所では、被災者が真冬の寒さにさらされ、災害関連死の要因の一つにもなったという。石破茂首相は、こうした状況を教訓に、学校体育館の空調設備整備のペースを2倍に加速する方針を示した。2024年度に「空調設備整備臨時特例交付金(仮称)」を新設し、地方自治体の空調設備整備を後押しする。
学校体育館は災害時の避難所として利用されるが、空調設備の設置率は依然として低い水準にある。24年度における公立小中学校での設置率は18・9%。中長期目標では、2035年度の設置率95・0%に向け、年間6・0%の進捗率が必要となるが、現在の年間進捗率は3・4%と低い。
自治体は、限られた財政の中で、近年続く猛暑への対策として、生徒が長時間利用する教室への空調設備設置を優先する場合が多く、体育館への設置は後回しになっている。学校教室は一時的な避難所になり得る一方、避難所として利用されたままだと、学校再開の妨げになってしまう。
文部科学省が新設する空調設備整備臨時特例交付金は、体育館と武道場の空調設備設置と断熱化に特化した交付金で、学校施設改善補交付金より手厚い支援となる。
補助対象は、避難所に指定されている公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程)、特別支援学校。
補助率は2分の1で、補助の下限額が400万円、上限額が7000万円となる。対象期間は33年度までの10年間。
交付金の対象となる体育館は、高い断熱性を備えている必要もある。一方、文科省の調査によると、公立学校の体育館などの施設3万3768カ所のうち、補助の要件を満たす断熱性がある施設は6413カ所と全体の19・0%にとどまっている。
断熱性能が低い場合は、交付金を活用して断熱化工事と空調設備設置工事を一括で行うことも可能だ。
24年は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が初めて発出された。各地で大規模災害への危機感が増しており、災害の発生に備えて、避難所の体制を十分に整える必要がある。
◆バックナンバー
▼ 2022年度(準備中)




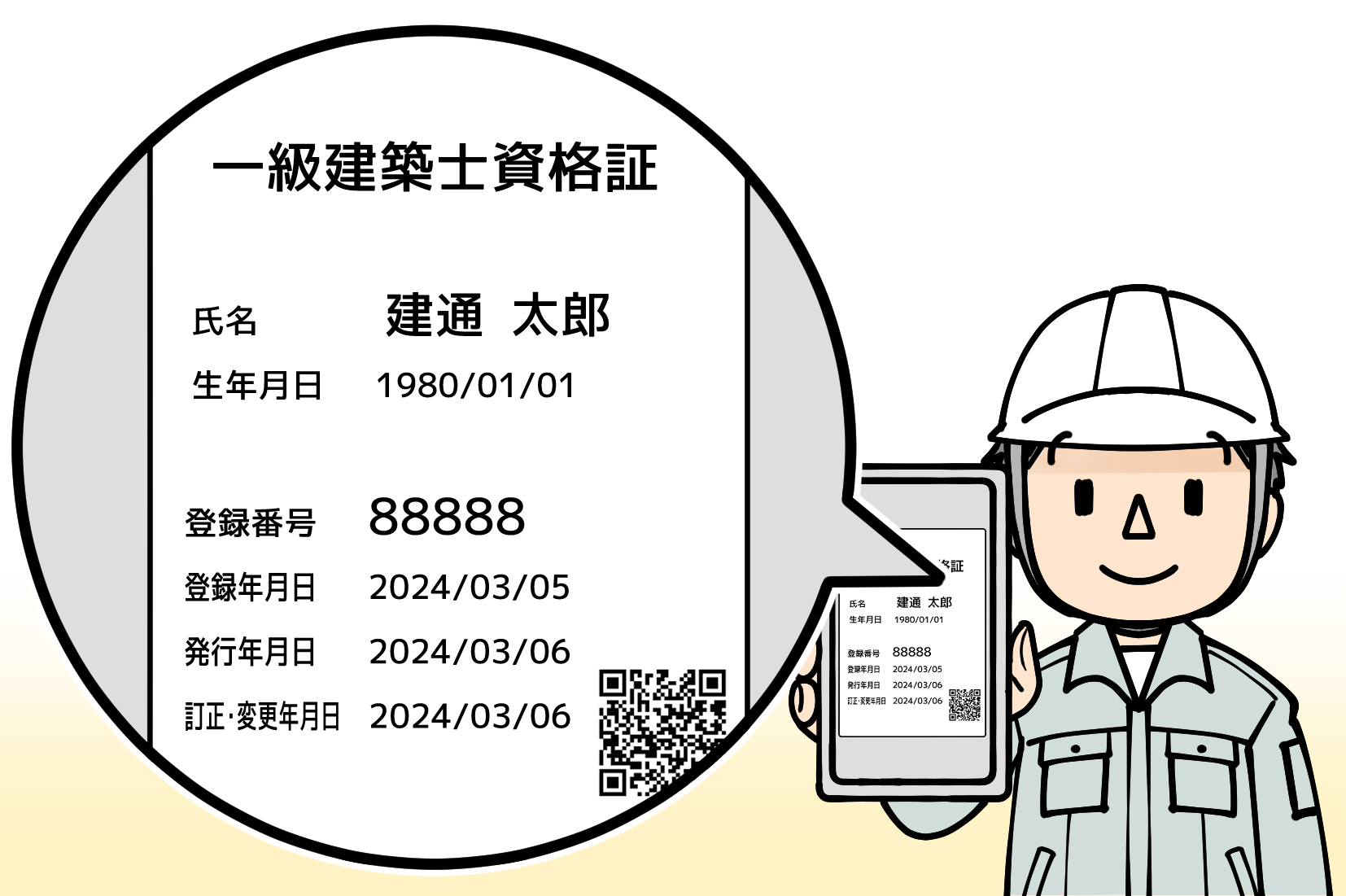
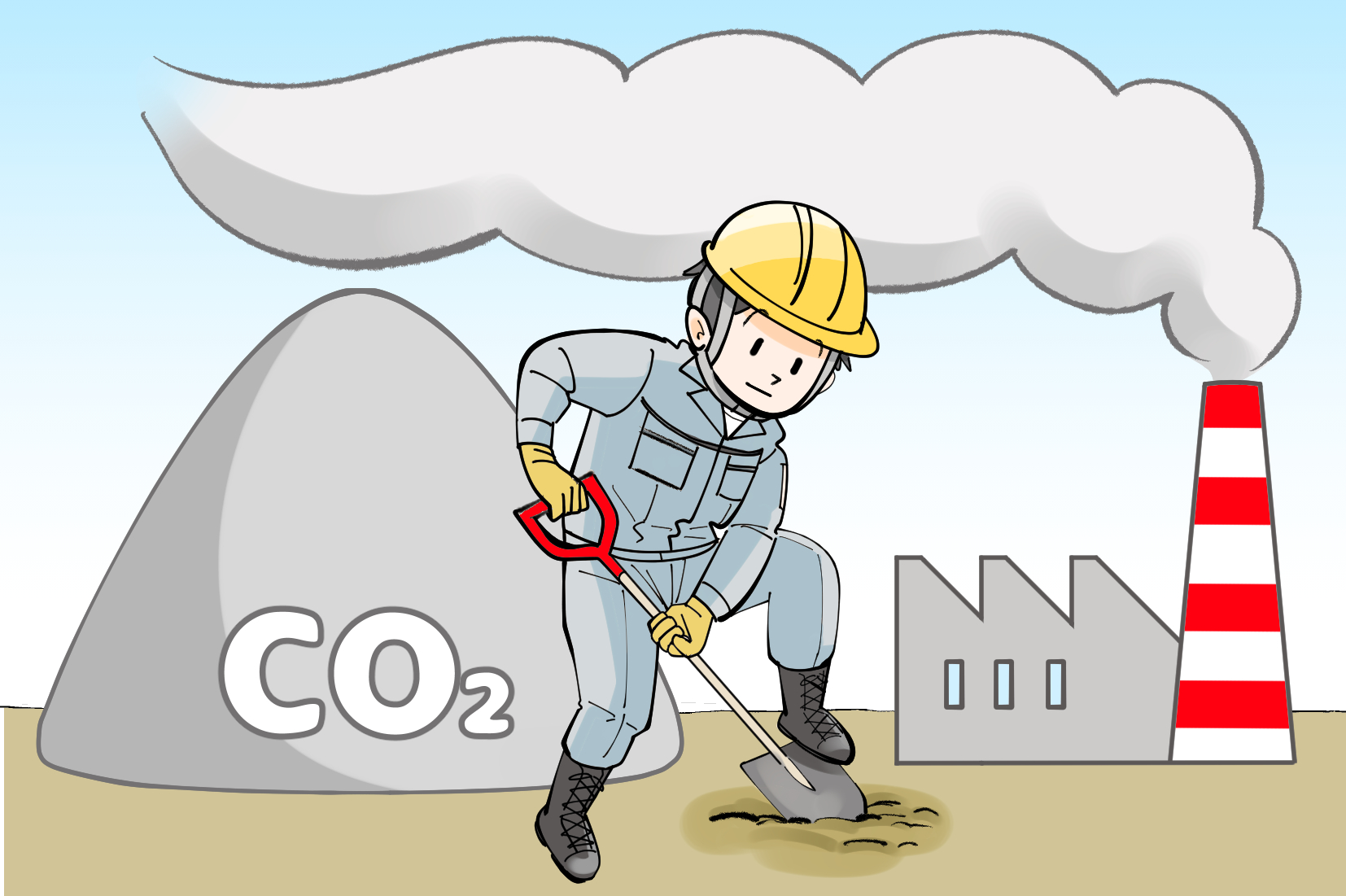





_1.jpg)



